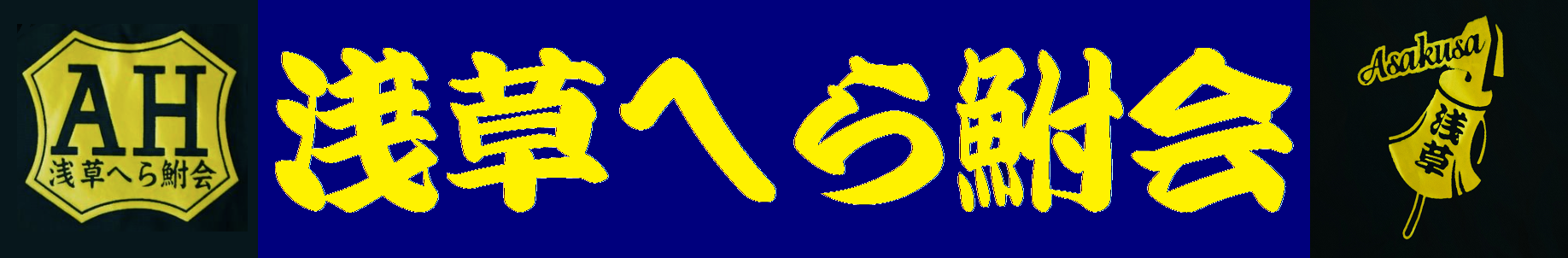
|
| TOP あゆみ トピック 例会日程 例会報告 年間成績 会員紹介 会員募集 成績集成 お問合せ |
| 歴史を飾った人々 |
|
叶 九隻(明29~昭52) 本名は叶定吉。 浅草へら鮒会創立者、初代会長。 現在の浅草ビューホテル近くで キンヘイ薬局を経営。 豊かな商才に恵まれ、当時の鉄道省内に店を出す一方、工場の昼休みを利用して外交販売を展開して大繁盛。 店へ遊びに行くと、化粧品会社の美人マネキンが大勢くつろいでいて、目の保養になったという。 鶴を思わせる痩身は優しさに満ち、性格は穏やか、誰も氏の怒る姿を見たことがなかった。 練れた人柄は会の内外を問わず、多くの人に慕われたのである。 釣技は…技術は知ってる、道具は持ってる、新エサにも研究熱心。 ぶんぶん振り回す竹竿の19尺に掛かってくるのは藻ばかりであったが…。 しかし、上手下手を離れて、人を引き付ける。 氏から声が掛かると嬉しくて「お手伝いしなきゃ」という気持になる。理想の指導者であった。 |
|
佐藤 紫舟(昭2~平8) 本名は佐藤和夫。 浅草へら鮒会二代目会長。 叶九隻の愛弟子。しかし、釣りの腕前は師を遥かに越える。 当初は鉄工所を経営、後に算盤塾の先生に転じる。算盤の2文字が示すとおり抜群に頭の良い方であった。 規律に厳しく、喜怒哀楽が激しく、よく怒り、万座の中で怒鳴られた人多数。 例会の帰路、交通ルールを軽んじた会員を見つけ、後で怒ったという話も残っている。 しかし、情のある怒り方であった。 個性的な人だからこそ、個性豊かな会員達を統率できたのかもしれない。 弁舌もさわやかで、一度しゃべれば「右に出る人はなかった」。 その指導力は日研理事長としても生かされ、同氏の下日研は1万2千人体制を築く。 熱意をもって会と日研の発展に尽くしたのである。 「紫」の名で知られる、へら浮子作者でもあった。 |
|
増田 逸魚(大5~平7) 浅草へら鮒会の創成期の様子が分かるのは、創立四十五周年特集号「四十五年の歩み」に記された、氏の記事のおかげ。 ペンだけでなく、絵筆にも優れていた。 俳優・山村聰が銀座に開いた釣具店ポイント店員、「へら鮒三国志」著者、スーパーダイナミックと名付けられた浮子作者、エサの開発者、そして銀座へら鮒会でも活躍。 つまりは「へら鮒釣りで生きていた」のか、本業がよく分からない。 素敵に不思議な人であった。 色男で、アメリカ風の粋な紳士で、チョビ髭がカッコよく…増田逸魚のようになりたい、そう思わせる人であった。 |
|
和田 敬造(大14~平8) 浅草へら鮒会で育ち、のち心血を注いで関東へら鮒釣研究会を育て上げる。 亀有駅前の紳士服専門店「マルワ」の経営者でもあった。 その人柄と業績は、門倉親水著「へら鮒いく山河」に余すことなく記されている。 釣りにおいては、佐藤紫舟と並ぶ叶九隻の愛弟子で、昭和40年の日研団体トーナメントにおいては主将として活躍。 試釣を重ね、作戦に心を砕き、決勝戦で紫水会・亀有・池上を破って浅草に優勝をもたらし、創立20周年式典に花を添えた。 佐藤紫舟と同じく威勢がよく、個性に溢れ…両雄並び立たずだったのかもしれない。 結果、浅草も関べらも発展したが、「もし二人が手を携えて進んでいたらどうなったろう」そう思われてならないのである。 |
|
青山 文男 浅草の花屋敷でトランペットを吹き、後には国際通りで焼鳥屋さん。 公潮会の幹事長から浅草発会と同時に初代副会長に就任する。 恰幅のよい温厚な人柄で、日研でも創立当初から活躍。植木義夫、山口幸司郎に続く理事長に推挙されたが固辞。 |
|
須藤 健作 浅草の料亭「福島」の主人。陸釣りの時はシャベルで土を掘り、肘掛の付いた座席を築城する。 安食水郷一帯の釣り場地図も発行、農家、小橋、ヨシ、マコモなどの案内図は見るも楽しく人気があったが…ないものも描いてあり、読者を困らせた。 愛すべき大言壮語の傾向があり、報知新聞の釣り担当として釣況を幾らか水増して発表。 叶九隻会長の元に「将監川、手賀沼、どこへ行っても、報知新聞の話はあれは浅草ホラ鮒会情報だと仲間内で話合っている。 まだまだ三貫目釣ったなんて記事を出しますか…」という読者の御手紙が届いた由。 セルトップに蛍光塗料を塗った「アンドン浮子」で一世を風靡したことでも知られる。 |
|
杉本 敬次朗 初代幹事長。 何時も一杯入っているような顔付で 口調も歯切れよく、宴会の席では必ず座布団を指の先でグルグル廻す曲芸を披露する。 骨董店の主人で、商売物の刀をいじっていて大怪我してしまい、12針縫ったことも…。時にバーや釣具店を経営。 一時は継ぎ浮子を作っていたこともあった。 |
|
金久保 光魚 二代目幹事長。 和裁の先生、小唄は名取「梅久」として踊りもこなす。 毒のない人柄から出るひょうきんな駄洒落で、大勢の仲間を笑わせてくれた。 普段座っての仕事なので歩くのが苦手。横利根では中島屋の舟小屋の前が「近くて良い」と定位置であった。 以前は真鮒釣りに打ち込み、その時の癖で、トーナメントの選手として北手賀沼で釣った際、マキエサを投入。 相手方に見つかり「失格」の憂き目に遭ったことも…。 糖尿病が悪化し、昭和45年、57歳の若さで逝去。 |
|
熊沢 勝二郎 瀬戸物屋さん、ごついオッサンであった。 釣り方は大バラケを打ち、そのエサが小さくなるまで待ってから合わせる。 何時も大型賞を獲っていた。 |
|
星野 光男(明43~平7) 発会当初から、団体戦の選手の一員として大いに活躍した名人。 大阪でへら釣りを習得し、その昔、星野光男ほど、卓越された釣り技で知られた人はいない。 釣りに独特の感性があり、昭26~28年、3年連続で西東東と大関の座を獲得。 青山文男副会長にヘラの手ほどきもした。 トーナメントの際、佐藤紫舟と野田奈川水門の際で竿を振る。 自分ばかり釣れるため、佐藤紫舟と場所を入れ替わったところ…3尺と離れないポイントで、やはり星野光男ばかりが入れ食い! 釣場の開拓にも全国を釣り歩いて、その折の写真を多く残した。 それらの写真は、当時を知る資料として、貴重な財産と言っても過言ではない。 日研の後藤会長(初代会長)より、目方第壹位、宗村会長より、トーナメント第一位(浅草支部二組)、竿頭賞など、数多く表彰されている。 カバンメーカーとしても活躍し、今の箱型のへらバックを最初に考案し、世に出した職人でもあった。 |
|
竹野 紫泡 昭和25年、元旦から七日まで、六本松の平山に泊り込み、前の江湖で連日の貫目釣り。 釣り堀より釣れるため、帰るに帰れない。 ようやく同行者に電報が来て水辺を後にする。 一場所・二エサ・三に腕の時代に、エサの重要性を認め、気に入ったサツマイモが出来るまで奥様は八百屋さんへ通わされた。 昭和29年の例会では、6月、7月、8月と3ヶ月連続優勝し、5回の出席で関脇になっている。 名人として知られ、その「紫」の一字を佐藤紫舟は頂戴した。 |
|
金成 幸一 戦後再開した釣り堀、長原小池の三羽烏と謳われた。 駅前の商店の子息で、昼は釣り堀、夜は徹マン。親から勘当されそうになる。 竹野紫泡に「例会にはポイントを教えてあげる。君は釣るだけで良いから」と誘われ、釣り堀しか知らぬまま入会。 昭和29年、東大関を獲ったら…1年で退会してしまった。 |
|
渡辺 渡 元陸軍中将。 会員・鈴木芳夫が経営する築地の料亭のお客。 横利根・平勝の当時の御主人は元上等兵で…氏の前では「閣下」と最敬礼で弁当を出したという。 或る時、俳優の山村聰が銀座に開いていた釣具店「ポイント」に来店。同じく元上等兵の山村聰は「あれが将軍!」と其の一挙一動を見つめていた。 山村聰にとって、これが後に映画「トラ・トラ・トラ!」で山本五十六海軍中将⇒大将の演技として、花開く亊となる。 |
|
横井 英夫 料理の師範=今でいう料理デザイナー。 自分でデザインしたお皿やお碗を特注で作らせ、季節の料理を添える。 横井魔魚の釣号で知られた。下町っ子だが、浅草より銀座風な人。かってのモダンボーイであった。 後に銀座へら鮒会の会長に就任。 或る冬、浅草の会員が横利根で大型を掛けた。竿が満月になり、やたら重い。といって糸を切られる程の力はない。 水面に上がってきたのは、尺べら+少し前に川へ飛ばされた横井会長の銀座の赤い会帽であった。唯一の優勝バッジがついていた。 例会には栄太郎の和菓子や千疋屋のマッカートブドウに魔法瓶持参で参加。 お茶を入れ「休憩タイム」とやってくると、竿を置いて付き合わされた。 |
|
戸田 粂男 元は職人の実力派、行動派。軍隊生活も長く、中支を転戦する。 体力抜群だが小回りも利き、短竿に極細トップの繊細な釣り。 農家に手土産持参で顔つなぎして小舟を確保、更に年間例会連続出場記録も持っていた。 そして、午前中釣れないとさっさと汽車に乗って帰ってしまう。 女性達からとても慕われ、忙しかったのである。 川崎支部の会長、日研寿会の会長も歴任。 4枚合わせの太いボディにワカサギが釣れるようなグラスムクのトップを付けた「まこも」銘の浮子作者でもあった。 |
|
加瀬 一夫 天才「加瀬流」として知られる。 昭和38年度・同41年度、西大関、昭和39年度、東大関。 細く長いハリスに小バリ小エサのふかせ釣りで横利根に君臨。 鮎バリをヒントに此処から関東スレが生まれた。 「当時は小べらが沢山自生してたから通用したんだな」と本人が語っていた。 学生時代は「みずも」銘の浮子を作ってアルバイト、卒業時には「浅草の例会日に平日の休みが取れる」という理由で外資系の広告会社へ就職。 後には塾で子供達を教える一方、紀州を訪れて竿師たちと交流し、自らも竹竿を作っていた。 銘は「如月」「葉月」など完成した月の名の脇に一夫作。 繊細な釣りの片鱗と独創性は晩年にも見られた。 極薄の板オモリとしてブランデーの口金を使用。 学校の釣友会の後輩に、練馬の釣り堀・金木園にて「おい、レミーマルタンのオモリだぞ」と披露してくれたのである。 その一方「名人と子供は太い糸で釣る」の言葉を遺し、また冬の釣り堀では「魚を動かすのだ」と竿で水底を掻き回すお茶目な一面も見せた。 「馴染み際で触らなければ、直ぐに切り返せ」「同じポイントへ打てるよう、バケツを置いて練習」等、様々な言葉を思い出す。 中で白眉は「君の釣りは壊れた時計だな。まあ一日に2回は合うか」であった。 |
|
田坂 保(昭2~平10) 月刊へら専科創刊当時の「例会必勝・私のエサ作り」に登場。 その紹介によれば、愛媛県は来島海峡に近い浜育ち。幼い頃から磯や近所の池で竿を振っていた。 青雲の志を抱いて状況、昭和26年には早くも独立し機械工場の経営者となる。 この頃、義兄に誘われ浮間の釣り堀へ出掛けたところ天性に恵まれていたのか、義兄より沢山釣ってしまい、以後この道に打ち込む。 昭和35年にはうきもへら鮒会、昭和40年には日研紫水会に入会し石原正雄・佐藤徳通など名人達人と覇を競う。 浅草でも三役の常連で、昭和56年度には西大関。温厚かつ筋を通す人柄で人望厚く、お酒も強く、経済力に優れ、日研でも企画事業部長や地方部長として活躍。 存命ならば「日研理事長だった」かもしれない。 趣味も多才で、中でもさつきの盆栽はプロ級の腕前であった。 |
|
稲益 真琴(昭5~逝去) 同じく、月刊へら専科創刊当時の「例会必勝・私のエサ作り」に登場。 紹介によれば父が朝鮮総督府に勤務していたため、ソウルで生まれる。 春先にクリークの氷が溶け出すと、竹竿に木綿糸をつけ御飯粒をエサに朝鮮ブナやナマズを釣る。 昭和13年に板橋区へ転居、昭和35年頃からへら鮒釣りに熱中し、杉田富弥さん(北斗へら鮒会。オカメの原案者として有名、浅草にも在籍)と釣り堀を釣り歩き、当時は買い取り制で…最初から寸志を差し出すところもあった。 当初は電気屋さん、後に「真琴」銘の浮子でプロ作者として活躍する。 釣りの腕前は小場所・小エサに強い天才肌で、昭和40年度、同53年度の東大関。 浅草の歴史に残る名人の一人。そして、遊び人風の粋な人であった。 |
|
島野 清(昭13~逝去) 北斗へら鮒会、ゴールデンクラブでも活躍。 積極的なエサの手直し、タナの変更がズバリズバリ当たっていく切れ味の鋭さは「他に類を見なかった」。 月刊へらの新釣り技エッセンス(昭和56年1月号)の権現堂幸手園の記事に登場した折は、四ノ島前で丈4の底釣り。 底が悪くて気に入らず、イレパクになりかけたところで、顔を出した鈴木彪(元、野田幸手園)の「もう1杯右がいいみたいよ」の言葉に、いともあっさりと移動。 更なるイレパクを演じ、編集子をして「参りました!」と言わせる。 昭和50年度の東大関。 今も氏を「名人だった」と語る人は多い。 |
|
佐藤 徳通(昭8~平20) 「ミスターへら鮒」と呼ばれた近代へら鮒釣りの祖。 効果抜群のペトコン餌は「常人では打てなかった」と言われる。 昭和42年~45年、佐藤紫舟・和田敬造・稲益真琴等が居並ぶ中で4連覇達成。 昭和42年8月例会時、山中湖における9.02kgは同年の最多重量、昭和43年5月例会時、佐原向地例会における10.78kgも驚異的と呼ぶ他ない。 後に北斗へら鮒会およびゴールデンクラブを立ち上げ、更には昭和63年~平成3年まで、日研理事長を務めるなど、釣技にとどまらず、へら鮒釣りの発展に大いに貢献した。 そして、見かけはゴツイが、近所の中学生が遊びに来ると優しく教え、帰りには自作の浮子「小春」をプレゼントするおじさんでもあった。 |
|
荒木 宏正(昭7~平22) 若年の頃より名手として知られ、昭和42年2月例会時、横利根川にて4.94kgを釣って初優勝、年間9位(年間優勝は佐藤徳通)。 更に昭和44年5位、45年6位、46年6位、47年3位と着実に順位を上げ…昭和48年度の総釣果56.13kgにて遂に年間優勝を獲得!以後も三役の常連として活躍を続ける。 あだなは申年生まれから「モンちゃん」。 「多々島エコのモンちゃん」と謳われ、得意は小べらの数釣り。そして、浅草の制服が良く似合う、普段の姿も御洒落な釣師であった。 一方、竿の銘柄には全くこだわらず、丈8など、手元にある故障した竿から適当につなぐため、時に3人の竿師の部分部分が集まって1本を成していたという。 晩年は常任相談役として浅草を見守る。 平成21年1月、弱った身体を支えられ「会員の姿を見る」そのためだけに新年総会に参加した姿は、一同の胸を打つものがあった。 |
|
須永 泰平(大11~平26) 愛称「スーパージージ」。 80歳の平成15年2月例会、清遊湖にて22.8キロ釣って優勝。 81歳の同9月例会、精進湖にて37.4キロ釣って優勝。 更に82歳の平成16年11月、名手の集まることで知られる日研の各部合同懇親釣会(野田幸手園)を34キロ釣って優勝。 何種類かを混合した秘密エサ「須永ブレンド」の威力であった。 そして「細胞の構成が違うんじゃないか」と思いたくなる元気は人々を驚かせた。 日研では文京支部を育て、渉外部で活躍。浅草では常任相談役として最後まで会を見守る。 若年より非鉄金属の世界で働いて成功を収める一方、地域(文京区後楽)の防犯活動への貢献により、平成23年には藍綬褒章を受章。 健康と経済と名誉に恵まれた、誰もが憧れる人生を送った方であった。 そして、何でも出来る立場にありながら「ひたすら妻を愛す」真面目な方であった。 今も大声の元気な挨拶が耳に残っている。 |
|
杉田 草舟(昭10~逝去) 本名は杉田英和。 浅草へら鮒会、三代目会長。 生まれも育ちも浅草。 御仕事は文房具屋さんから、児童減少を受けて店をビルに建て替え、ファミリーマートへ転業。 国民学校3年生の時、宮城県の鳴子温泉へ学童疎開し、土地の子ども達とミミズで小鮒を釣ったのが初めての釣り。 東京へ戻り、ハゼ釣りが好きだった父が、店を訪れた叶九隻に「息子は鮒を釣ったんですよ」と話し、「そうか、見込みあるなぁ。遊びに来なさい」となり、浅草へら鮒会との縁が生まれた。 佐藤紫舟会長の下で昭和56年より幹事長を勤めた。 佐藤会長の死去に伴い、平成8年、三代目会長に就任。 大勢の会員に慕われ、穏やかな人柄の良き会長であった。 |
|
櫻井 呑舟(昭10~令1) 本名は櫻井春夫。 「オカメの呑舟」として知られ、オカメの商品に「呑」の名を遺す。 進取の気風に溢れ、IT企業の経営者にして、麻雀店や喫茶店も運営していた。 何故か、昭和59年の入会時、浅草の親分として知られる仲初(なかはじめ)会員に「あんたカタギじゃないねえ」と言われ、その事を後年まで嬉しそうに話して下さった。 元気で釣りには真面目かつ熱心。 相談役として、常に浅草へら鮒会を厳しく優しい目で見つめていた。 新年総会の挨拶では、「1年間また頑張ろう」と奮い立たせてくれた。 |
|
三原 義雄(昭7~令2) 豊島区において三原屋米穀店を経営。 12歳の時、池袋に近い大谷口の釣り堀へ一人で出かけ、後に同所で杉田富弥(北斗)、稲益真琴(浅草)の名手2人と知り合う、 昭和42年入会。 翌々年の昭和44年、4月例会の佐原向地で7.02キロ、11月例会の佐原向地及び潮来で10.78キロ釣って優勝。年間成績も4位(西関脇)と三役入り。 特に11月例会時、利根本流(石納あるいは大橋)において、振出グラス竿の21尺に3~4mのバカ出しをして、バカ投げで打ち込んでの釣果は人々を驚かせる。 エサは裏漉しの焼き芋を水で緩め、小麦粉で締めたもの。 なにより、浅草の例会が佐原向地で年6回組まれていた頃「佐原に200日居ました」。 力強い釣りで、昭和50年代には日研トーナメントの主将として浅草を引っ張り、西武サースデイクラブでも活躍。 殊にオカメの釣りには定評があった。 そして、令和元年9月11日、千代田湖例会において、24尺ドボカメで、28キロの優勝。時に86歳。此の偉業は燦然と輝いている。 |
|
小池 忠教(昭20~令4) 浅草へら鮒会を愛し、浅草の例会をなによりの生き甲斐として、生涯現役を貫いたへら鮒界の第一人者。高校球児で、早稲田実業で甲子園への出場を果たす。 その俊足をかわれ守備はセンター。準決勝の最終回で飛んできたフライを捕れば勝てたのだが、なんとライトの選手が突っ込んできて衝突し、落球。サヨナラ負けとなる。 「黙って俺に任せとけばよかったんだよ」と、晩年まで悔やんでいた。 その後、日大へと進み野球を続けたが体調を崩してしまい野球の道を断念。大学卒業後は広告代理店勤務を経てそのまま経営者へ。 その頃からへら業界で頭角を出し始める。会社をたたみ、しばらくの間は例会送迎の「白バス」で生計を立ていた。 「よくあんなオンボロバスを運転していたよと」と笑っていたが、その苦しい時代、五月へら鮒会の飯島会長から仕事を多く回してもらう。 錦糸町に集合しての出発が多く、会長の家で晩飯をいただき仮眠するという生活が続き大変お世話になっていた。 「だから俺は飯島さんに一生頭が上がらない」と、いつもしみじみと口にしていた。 浅草へら鮒会入会年に長竿を使った釣りで周囲を圧倒する釣果を叩き出し年間優勝。 以降、しばらくの間「長竿ボーイ」と呼ばれていた。そして、1984(昭和59)年5月、ヤマでの例会で、西湖・前浜東電流れ込みにて55.6kgの大釣りを筆頭に次々と高釣果を叩き出し、佐藤徳通に次ぐ2人目の「年間優勝3連覇」を果たす。本人いわく「会員が100人以上もいた時代だけど、まったく負ける気がしなかった」。 とにかく「浅草の例会命」で、例会に懸ける意気込みは時に「執念」すら感じさせるほど鬼気迫るものがあった。その唯一無二の釣りセンスで例会での爆釣は数知れず、「得意な釣りがあってはいけない」というのが例会師としての持論で、寒中における横利根川での中通しの非常に厳しい釣りからヤマでの長竿チョーチンや底釣りの両ダンゴまで、どんな釣りでも高次元の釣技を持ち備えていた。 また長年に亘り専門誌での連載を持ち、多くのへら鮒釣りファンに「へら鮒釣りの真髄」を伝授。刻々と変化するへら鮒の寄りや食い気、その状態へと常にエサを合わせていく両ダンゴ釣りには目を見張るものがあった。 なにより、釣り場で実際に釣ってみせるその「本物の釣り」に魅了されて、浅草の門を叩いた会員も多い。いつも本気だからこそ「伝説」も多く、釣宿で寝ていながら(へらを釣る夢を見ていたのだろう)竿を絞っていたり、雨の中パラソルも差さず(基本的にパラソルは嫌いでよほどのことがないと差さなかった)に釣りをしていて、グルテンを上着のポケットに入れて使っていたり…また、気合いが入りすぎてしまうのか時に試釣であまりにも釣りすぎてしまい、肝心の本番で釣れないということもよくあった。長年インストラクターを務めていたエサメーカーがなき後、個人で「ベーシック」を立ち上げ。以後、10年間「釣り人が作ったエサ」として製造販売を続けた。 もちろん、その間も浅草の例会だけは欠かさず出席。 工場でお麩にまみれながら夜中までエサを作り、そのまま例会に向かうという月日が続いた。 なかでも特筆すべきは、配達用の会社のライトバンが盗難に遭ってしまい、運悪く釣り道具一式を積んでいたため、そこからしばらくは10尺と21尺の2本の竿しか持たずに例会で勝負していた。 その「小池魂のエサ作り」は以後、モーリス(現・バリバス)、そして村上製麩へと受け継がれている。若手の時代から幹事長を務め、2008(平成20)年に浅草へら鮒会四代目会長に就任。以後8年間、浅草へら鮒会のさらなる発展のために尽力した。 2022(令和4)年11月8日23時過ぎ、逝去(享年78歳)。翌9日、最後の愛弟子となる福冨大祐が三年連続年間優勝を成し遂げる。 まだ多くの夢を残しつつ、そのへら鮒釣りに捧げた人生にそっと幕を降ろした。 墓前には生花とタバコ、そして大好きだったコカ・コーラがいつも供えられている。 |
| TOP あゆみ トピック 例会日程 例会報告 年間成績 会員紹介 会員募集 成績集成 お問合せ |
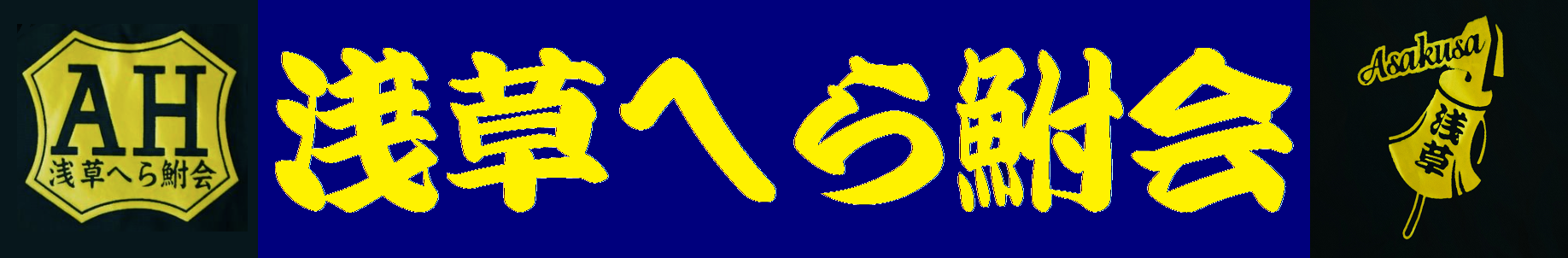
|